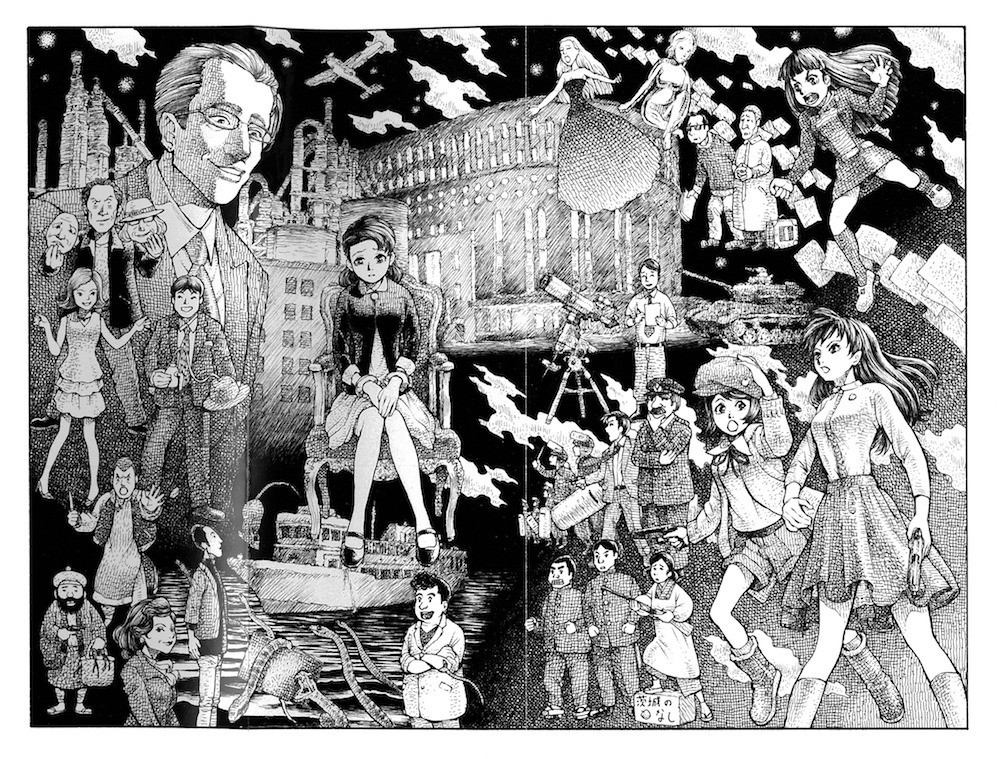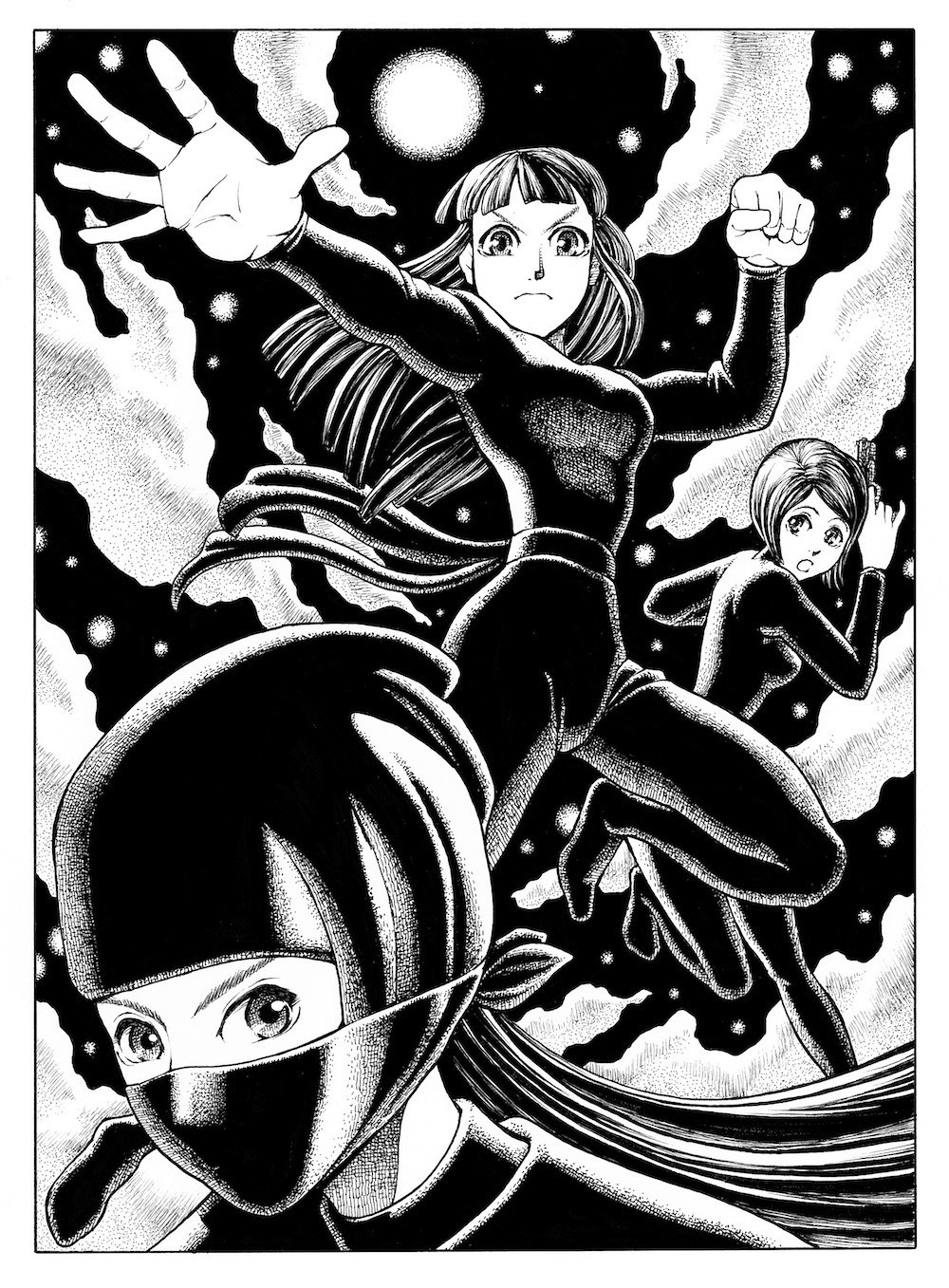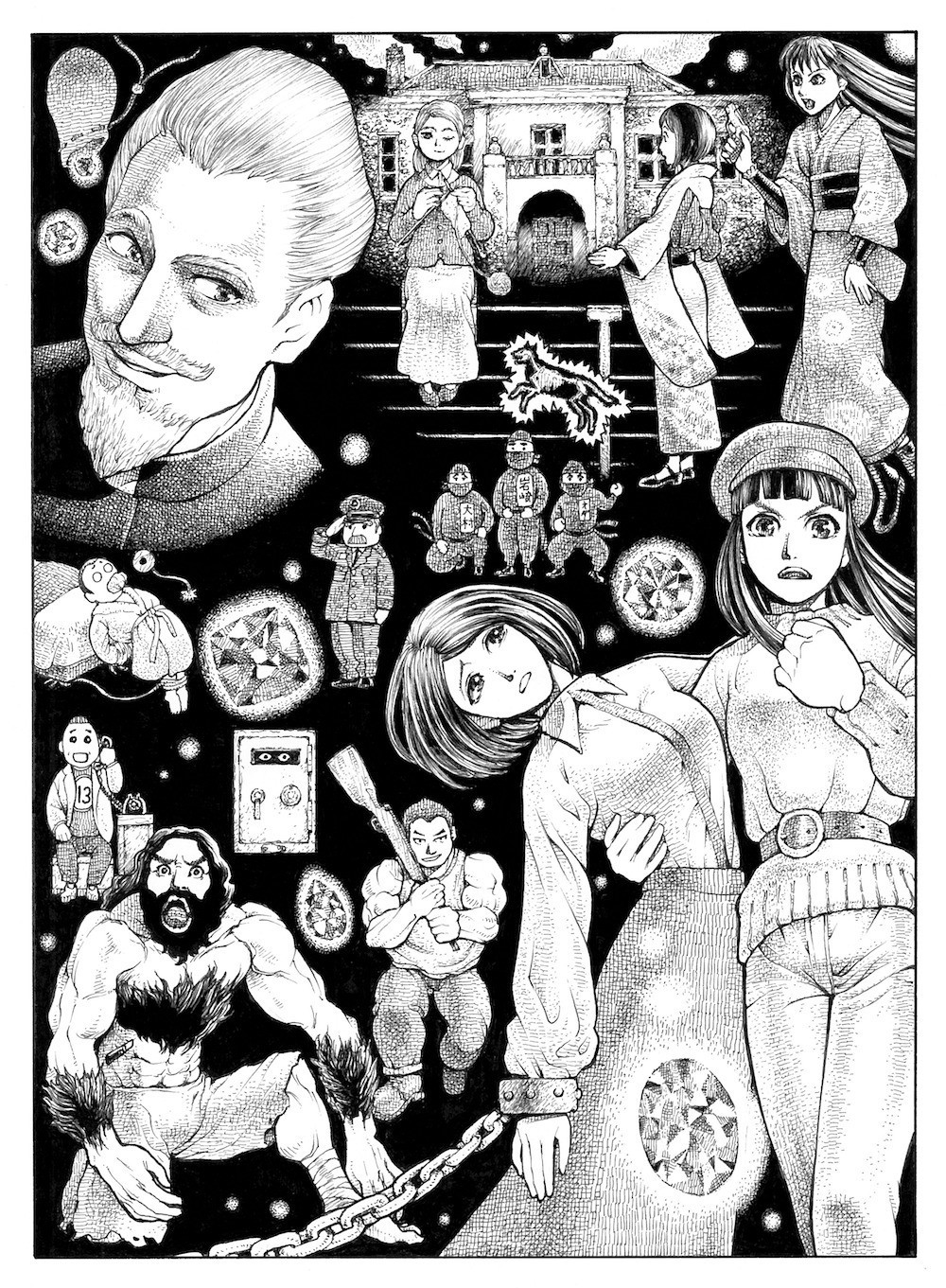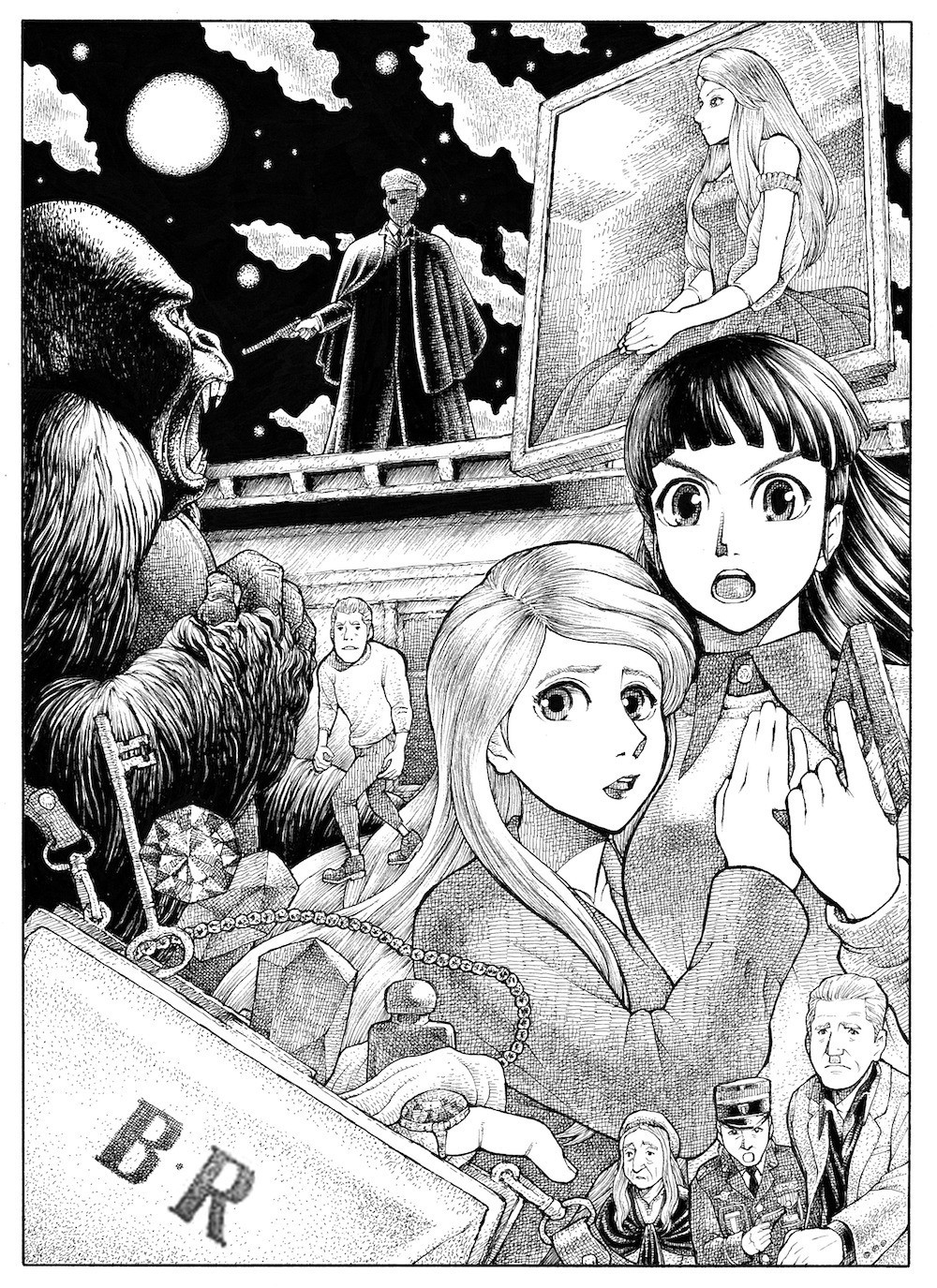新説三国志/尾崎士郎(河出新書,1955)
尾崎士郎といえば、戦前・戦中・戦後にわたって活躍した大作家で、『人生劇場』で一世を風靡したことで知られる。東京と愛知県の二箇所に記念館があり、文豪と言ってもいいだろう。
この本は古本でたまたま見つけて買ったもので、新書版、200ページ程度の薄い本。三国志を語るにしては妙に短い。もともと「三国志」ものに興味があったから買ったので、尾崎士郎の名前で買ったのではない。
とはいえ、何しろ大作家の書く三国志だから、どんなすごい作品かと思ったら…。
これがとんでもないシロモノで、怪作としか言いようがない。どこからつっこんでいいのかわからない。
登場人物のセリフが完全に現代語だとか、地の文に「テーブル」とか「ジャック・ナイフ」とかやたらカタカナ語が出てくるとか、それどころかセリフにまで「オー・ケー」とか「サンキュー・ベリー・マッチ」とか英語が混じる。
しかしそれはまだいい。基本設定に矛盾があるのは困る。
例えば、諸葛亮が初登場する時の年齢設定がおかしいとか。「まだ三十には間があると思われる年配であるのに、細長い顔に粗髭をのばし」などと書いてあるが、この時はまだ物語の序盤、何進が暗殺される直前なのである。とすれば189年、孔明はまだ8歳のはず。いくらなんでも年齢が違いすぎ。
何よりも、ストーリーが何だかおかしい。肝心なところをはしょりまくっていて、話のつながりがめちゃくちゃになっている。黄巾の乱の後、劉備は督郵をぶん殴って行方をくらまし、いつの間にか流浪の軍団の長となって荊州に出現する。その間、呂布も出てこないし官渡の戦いもない。劉備と曹操とのからみも一切なし。
そして話は、劉備が諸葛亮を軍師に迎え、新野に曹操軍を迎え撃つ直前で唐突に中断する。作者のやる気がなくなったのかと思ってしまうような中途半端な終わり方。
まったく、なんじゃこれは、と言いたくなる小説だった。ある意味すごい。
実は尾崎士郎の小説、他には1冊も読んだことがない。まさかこんな変な話ばかり書いていたわけではないだろう、と思いたい。