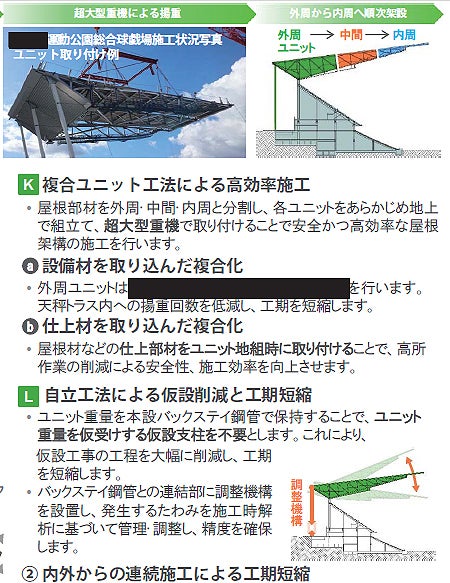5: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 09:56:36.10 ID:0jrETwIk0.net
巨人これ来年マイナスやな
47: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:09:06.16 ID:hysTdBLC0.net
>>5
由伸効果で少しは伸びるやろ、原効果なんてマンネリ過ぎてなくなってたんやから
8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 09:57:05.19 ID:UCOzQMsT0.net
ファンは3人から何倍に増えたん?
30: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:05:31.69 ID:mEIlcgNy0.net
>>8
少なく見積もっても二桁はいるにちがいない
11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 09:58:08.21 ID:1itBwo0/0.net
一試合減ったのにな
12: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 09:58:50.57 ID:sbtM2C35p.net
西武って意外と少ないんやな
16: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 09:59:53.97 ID:fGwYwLOR0.net
全球団増えてるってのは良いことよ
22: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:02:00.49 ID:4RL6ulnJ0.net
ずっと最下位で増加は頑張ってるな
23: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:02:12.80 ID:ghnROm44K.net
阪神って別に言うほど人気じゃないのな
26: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:03:41.20 ID:9qITaTFu0.net
>>23
和田になって客減った
24: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:03:06.61 ID:32nhhm3pd.net
大補強したのになぁ
27: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:04:53.29 ID:Mdr3k7Hga.net
中日ってまじで増えてんの?
32: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:05:53.27 ID:zL76+sIs0.net
>>27
地方減ったから増えたのは間違いない
引退試合興行は満員やったし
29: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:05:29.95 ID:LlUL1eYid.net
中日はこのへんが下げ止まりなんやないの
31: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:05:37.19 ID:IIr4bvLGK.net
しょっぱい試合ばっかでなんであんなに入ったのか意味わからんわ
34: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:06:26.85 ID:FdleB9qI0.net
Deは伸ばしてこれかいな
はよ球場拡張せなアカンな
42: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:08:25.63 ID:oqA8hco0E.net
前の年に一位逃しの二位だったんで
年間席まとめ売りの営業が捗っただけでは?
38: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:07:39.76 ID:+tJ6YTMA0.net
今年の増加分=2位になった時のニワカ
と考えると来年は減るだろ
39: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:07:40.56 ID:r5MuGDFdr.net
キャパの影響はあるやろ
あとロッテは来年平沢成田で大変なことなるで
46: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:08:40.86 ID:tEi3KiLi0.net
西武はアニメコラボが功を奏した感じなのか?これ見ると
49: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:09:34.78 ID:X9yO4EOj0.net
パの3番手って思うとすごい
54: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:10:02.33 ID:hrEGYKdSd.net
シーズン序盤大阪ドーム凄い入っててびっくりした
そしてびっくりするほど酷い試合をした
59: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:12:27.88 ID:k9AQydoU0.net
>>54
でもあの頃のオリックスわくわくしたよね
巨大戦力はエンジンかかるの遅いからwみたいなこと宮内が言ってたあたり
71: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:15:31.34 ID:vnBSZXGaa.net
これ人口とか考えると実質ハムが一番人気あるな
72: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:15:35.89 ID:PPQylrX20.net
ロッテは球場アクセス言うけどバレンタイン時代は人気あったやろ
73: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:15:44.41 ID:NFLhwl4da.net
地道に企業努力すれば人気はあげられるんや
それをわかってない不人気が多すぎる
81: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:16:57.46 ID:zgacp7e5K.net
糸井が来た2013年から右肩上がりが続いてる
84: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:17:13.32 ID:GaFJd8dcd.net
観客増えてるけどオリファンが増えてる感じ全くしないよね
97: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:21:36.68 ID:7ChB5B/I0.net
今年広島とオリックスが優勝してたらかなり盛り上がったんちゃうか
98: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:21:44.95 ID:2/yrEyoSd.net
野球人気が衰退してるってのはようは「巨人、大鵬、卵焼き」の時代が終わったってだけで日本のローカルコミュニティにおける文化としては普通に最上位だぞ
104: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:23:21.81 ID:k9AQydoU0.net
>>98
巨人人気が終わっただけで地方に分散しただけなんだよな
118: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:26:38.40 ID:r5MuGDFdr.net
>>98
ネットの発達でマーケティングの方法もテレビだけじゃなくなったから野球のなかでも趣味、文化の多様化が起きてる
野球といえば巨人という先入観がなくなって、普通に選手押し、地元愛が高くなったな
パリーグにスター選手が集まってるのもいいのかも
101: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:21:58.10 ID:Ue+JwBHNd.net
京セラ行くこと多いけど確かに5年前と比べたら客増えたわ
106: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:24:30.02 ID:2kIQhZns0.net
今年勝てかったのはあかんよな
来年怖い
110: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:24:53.31 ID:j5WbX7LM0.net
前年比みんな上がってる優しい世界
112: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:25:29.92 ID:TWsipUUd0.net
落合時代に観客のこと云々言われてた気がするけど増えてるんやな
114: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:26:20.42 ID:rYzNZpUBd.net
なお今年一番人の入りがよかったのは近鉄復刻南海復刻試合の平野が燃えた試合の模様
117: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:26:27.76 ID:gpGHKiPnd.net
阪神なんで増えてるんや
と思ったけど優勝争いしてたか
125: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:28:09.46 ID:RI0tQ0odK.net
ガラガーラで快適観戦が好きなワイには悲報や
135: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:29:29.56 ID:zRJZksre0.net
阪神の観客動員が減少していたという風潮
一理もなかった
141: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:30:29.98 ID:TcAK3vlv0.net
>>135
2005年 岡田 3,132,224人 平均42,907人(1位)
2006年 岡田 3,154,903人 平均43,218人(1位)
2007年 岡田 3,144,180人 平均43,669人(1位)
2008年 岡田 2,976,754人 平均41,344人(1位)
2009年 真弓 3,007,074人 平均41,765人(1位)
2010年 真弓 3,005,633人 平均41,745人(1位)
2011年 真弓 2,898,432人 平均40,256人(1位)
2012年 和田 2,727,790人 平均37,886人(2位)
2013年 和田 2,771,603人 平均38,494人(2位)
2014年 和田 2,689,593人 平均37,355人(2位)
2015年 和田 2,878,352人 平均39,977人(2位)
136: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:29:38.74 ID:q5jca6GKr.net
予定潰れたからどうせガラガラだし京セラ行こう!ってのがオリックスのいい所だったのに、チケット安いし
楽天対決オリックスとか最高やで
147: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:31:30.60 ID:q5jca6GKr.net
オリックスと楽天の広報の仕方とグッズ展開と企画はガチで有能だと思う
他球団が見習ったらもっと増えてるだろうなレベルで
155: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:33:08.49 ID:GsmtxcJJ0.net
オリックスは平日は大したことないけど土日の試合だと家族連れ需要でやたら客が入るようになった
166: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:34:37.63 ID:qIuNFTzOa.net
去年の大躍進で掴んだファンを一年で突き放す無能
177: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:36:46.88 ID:VQi/wtDbr.net
楽天が6.6も増えてるのはマジで謎
今年なんて終始シーズン面白い所無かったやろ
189: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:39:08.42 ID:k9AQydoU0.net
>>177
経営は優秀だからね
192: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:39:34.83 ID:Qiq38RxG0.net
>>177
広報が有能
地方開催でもスタッフ大勢連れて行ってコボスタと変わらない企画してる
補強よりスタジアムの設備と企画に力入れてる、観覧車とか作るくらいだし
パリーグで上がり幅ところは全部企画と広報が有能
183: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:37:57.13 ID:qIuNFTzOa.net
Bsgirlsが地味に成功してて草
あんなもん要らん思ってたのに
185: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:38:36.77 ID:VQi/wtDbr.net
>>183
意外と試合前に有るステージ盛り上がってるからな
154: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/12/26(土) 10:32:44.28 ID:7t3lPPKe0.net
全体的増えてええ傾向やわ



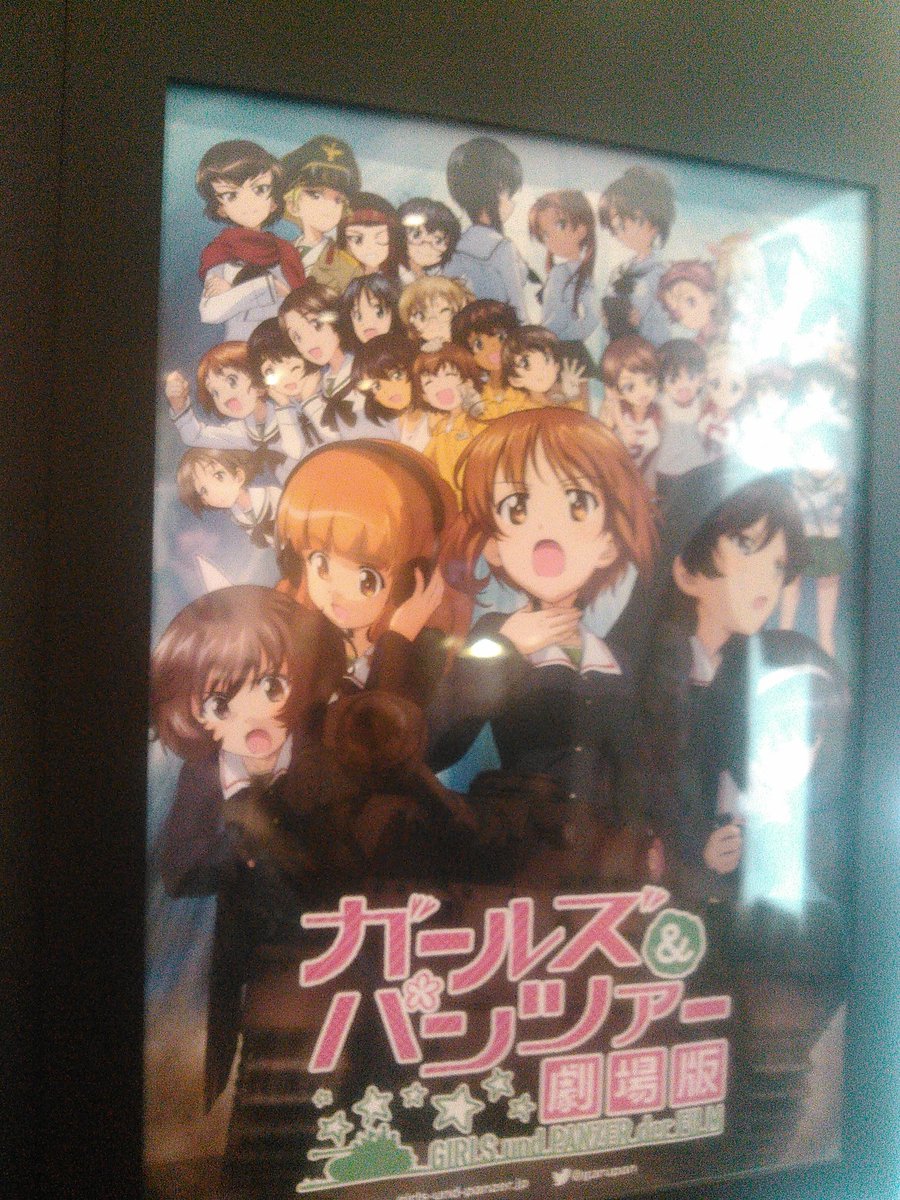
 九条先輩☆ひろし☆戦争法絶対廃棄!
九条先輩☆ひろし☆戦争法絶対廃棄! 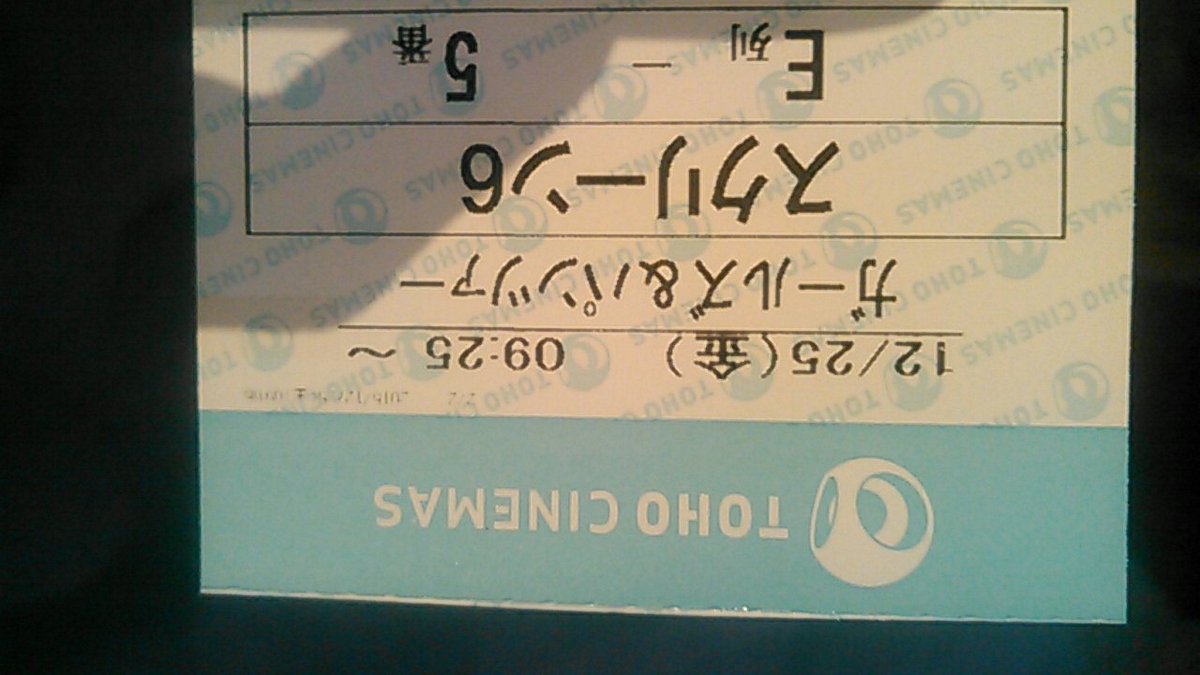
 女性人権の会会員
女性人権の会会員 



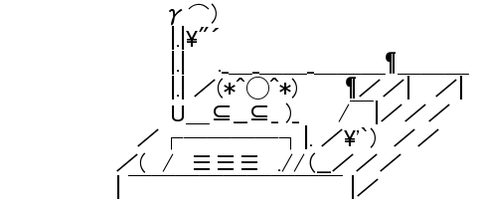

 崩壊たそ
崩壊たそ